政治経済の分野でノンフィクション作品を数多手がける作家 大下英治先生の新著『幹事長秘録』を読み始めて
全349ページあるうちの半分程度、145ページまで(第三章 平成の”喧嘩師”幹事長列伝)を読み終えたので、そこまでのおさらい。
内側から描く凄腕幹事長の実像
冒頭(「はじめに」で)、
政治経済の分野でノンフィクション作品を数多手がける作家 大下英治先生の新著『幹事長秘録』を読み始めて
全349ページあるうちの半分程度、145ページまで(第三章 平成の”喧嘩師”幹事長列伝)を読み終えたので、そこまでのおさらい。
冒頭(「はじめに」で)、
大横綱 第三十五代横綱双葉山の著書『新版 横綱の品格」を読了。
(著者名は執筆時/親方時の時津風定次)
昭和二十九年に引退され、当然、双葉山関の現役時の姿は知らないものの、不倒の記録六十九連勝であったり、
同記録が途絶えた際に残した「我、いまだ木鶏たりえず」であったり、
伝説の人物として長く脳裏に刻まれており、「実際、どんな人だったんだろう?」の思いを抱いており、
つい先日、著書(本書)が出版されていることを知り、入手した経緯。
淡々と双葉山関が生涯をふり返っておられる印象で、体格に恵まれているわけでもなく、
大横綱として地位を確立するまでは
先月(2018年3月)から近いインターバルで西村賢太さんの著書を2冊読了してみて
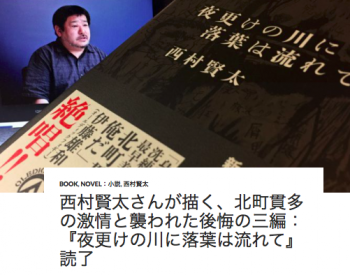
関連情報を検索しているうち、
amazon レビューに流れつき「代表作って、どんなだろう?」と興味が湧き、手に取った芥川賞受賞作品『苦役列車』を読了。
題名からだけでは、まず間違いなく手元に引き寄せることはなかったでしょうが・・
続きを読む 西村賢太さんが北町貫多を通じて描いた、人生の底辺を開けっぴろげに晒け出し、したたかに生きた生きざま:『苦役列車』読了
先日、中間記をアップロードした
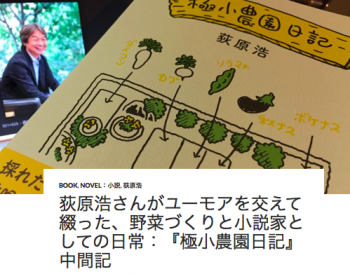
荻原浩さんの初エッセイ集『極小農園日記』を読了。
本書の存在を知り、サイン本であったもののタイトルに本の厚み(=296ページ)に及び腰となっていたものの
実際、読み進めてみると、タイトルに直結する家庭菜園、野菜づくりは 1章 極小農園日記 Part 1 <秋冬編> & 4章 極小農園日記 <春夏編> の2章で、
他は 2章 極狭旅ノートは新幹線車内サービス誌『トランヴェール』で『いまどこを走っている?』と題された2013年4月から2015年3月までの連載、
3章 『極私的日常スケッチ』は、雑誌、新聞に載せられた単発物や短期連載からのセレクション。
私と同じく阪神タイガースファンであるとの述懐に親近感を抱いたり、「あとがき」で
” あらためて読み返すと、けっこうあちこちで怒っていますね。”(p295-296)
と毒づく日常であったり(笑)
その中でも最も印象的であったのは。初小説にチャレンジされた時の経緯、心情を綴られた「小説に参戦」(p193-201)で、
” 過去のものになっていた泊まりこみを生活を再開した。締め切り近くの数週間は、一日おきに徹夜をした。
攣りそうな手にサロンパスを貼り、コーヒーの飲み過ぎで何度もトイレでゲロを吐いた。
忙しいことに慣れていたはずだったが、書くことがあれほど苦しかったのは、初めてだ。
だけどなぜか充実していた。ランナーズ・ハイならぬライターズ・ハイだったのかもしれない。
いま思えばビギナーズ・ラック(註:オロロ畑でつかまえて)としか言いようがないのだが、この処女作で賞を取ることができ、本も出版された。
一回でやめるつもりだったのに、その後八年、書き続けて、いつの間にか専業になった。”(p200-201)
抜粋であるため、前後をお読み頂ければ、より深い感慨に浸れると思いますが、
プロの小説家が誕生する一大決心といったライフストーリーも感じることが出来、本の厚みに伴う読み応えも得られました。
全編ではユーモア土台の野菜づくりとの格闘の模様、2〜3章では小説家の日常に、荻原浩さんの人がらに触れた感覚も得られて、
「書く」ことに興味を持っている人間として、良き出会いを実感できた一冊でした ^^
直木賞作家 荻原浩さんの初エッセイ集『極小農園日記』を読み始めて
半分あたりのところまで来たので、そこまでのおさらい。
本書は、
1章 極小農園日記 Part 1<秋冬編>
2章 極狭旅ノート
3章 極私的日常スケッチ
4章 極小農園日記 Part 2<春夏編>
という章立てのもと、主として雑誌の連載がまとめられたもので
小泉純一郎元首相が、自身の政治家としてのキャリアを振り返った『決断のとき ー トモダチ作戦と涙の基金』を読了。
先月参加した講演会↓の対象書籍で、
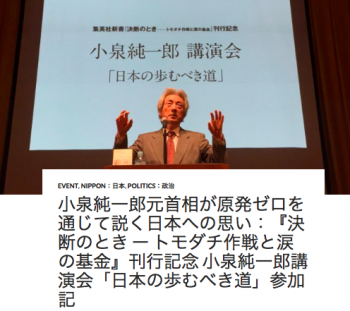
序章 ルポ・「涙」のアメリカ訪問記 常井健一
第一章 仁 小泉純一郎
第二章 義 小泉純一郎
第三章 礼 小泉純一郎
第四章 智 小泉純一郎
終章 「信」を問う 常井健一
という章立てのもと、主として小泉純一郎元首相が語ったことをかつて『小泉純一郎独白』を出版されている
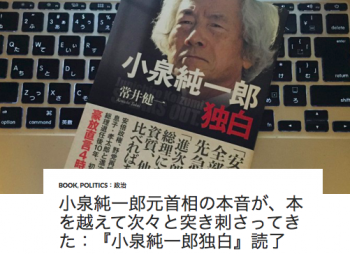
(取材・構成)常井健一さんが、まとめられて上肢された一冊。
序章と第一章は記述の重複が散見され、引っかかるところもありましたが、先日の講演会のテーマにもなった
「トモダチ作戦被害者支援基金」に、小泉純一郎元首相が携わることになった経緯がまとめられており、復習的な意味合いで読めました。
東日本大震災後、韓国行きを変更して復興支援に当たってくれた米兵の
続きを読む 小泉純一郎元首相が振り返った、議員活動を通じて実現しようとした日本への思い:『決断のとき ー トモダチ作戦と涙の基金』読了
『苦役列車』で芥川賞を受賞された西村賢太さんの『夜更けの川に落葉は流れて』を読了。
今年(2018年)1月、大雪に見舞われた日に八重洲ブックセンターで開催されたイベントで、
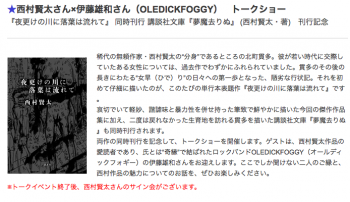
(イベント参加はしておらずも)後日、店置き用に書かれたと思わしきサイン本を見つけて入手していたもの。
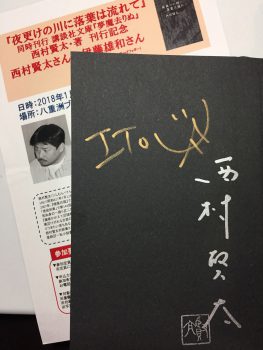
先日読了した『蠕動で渉れ、汚泥の川を』は全248ページながら展開されるストーリーに惹きつけられ読み易かったですが、
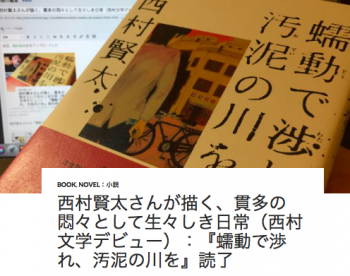
本書は三話収録で全181ページという構成に、それぞれの話しの面白さもあり、ペース良く読了に至りました。
最初の「寿司乞食」は、
野村監督こと野村克也さんの著書『究極の野村メソッド 番狂わせの起こし方』を読了。
先日参加したトーク&サイン本お渡し会の対象書籍として入手したもの。
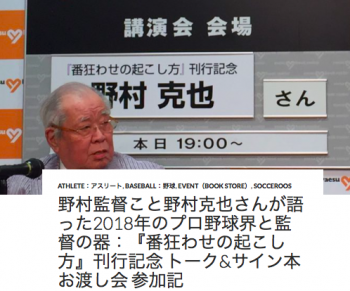
まず、タイトルを見て、昨年(2017年)出版された元千葉ロッテマリーンズの里崎智也さんの著書
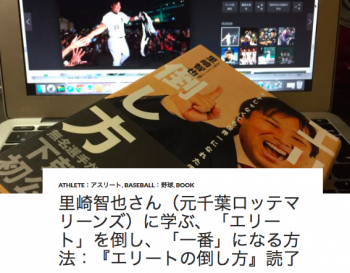
(『エリートの倒し方』)を思い出し、「(下克上的なこと)今、世の中で求められているトレンドなのかなぁ」と。
続々と出版されてくる印象の野村克也さんの著書、(時事ネタ以外)今さら新しいことと云うよりも
テーマによって、野村克也さんのお考えに切り込まれるアングルが異なるとの感覚ですが、本書では
続きを読む 野村監督こと野村克也さんに学ぶ、変わることを厭わず、頭と言葉を武器にして起こした番狂わせの法則26:『究極の野村メソッド 番狂わせの起こし方』読了