先日、読了記↓をアップロードした
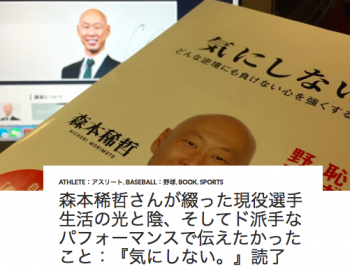
森本稀哲さん(元 北海道日本ハムファイターズ他)の『気にしないで。』の中に、
読了記を書いている時は全体量等との兼ね合いから割愛してしまったものの
お気に入りの箇所があって、それは↓「つらくても、「ほんのちょっと」が差をつける 」と題された項目で・・
先日、読了記↓をアップロードした
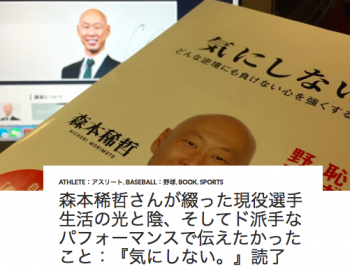
森本稀哲さん(元 北海道日本ハムファイターズ他)の『気にしないで。』の中に、
読了記を書いている時は全体量等との兼ね合いから割愛してしまったものの
お気に入りの箇所があって、それは↓「つらくても、「ほんのちょっと」が差をつける 」と題された項目で・・
先ごろ惜しまれながら引退した加藤一二三九段が、将棋界で前人未到の1,100敗を記録し、(出版時点)棋士生活60周年を迎えるに当たり、「負け」に焦点を当て上梓された
『負けて強くなる 通算1100敗から学んだ直感精読の心得』を読了。

7月末に参加したトーク&サイン会↑に参加すべく対象書籍のうちの1冊に選ばれていて手にした一冊。
本のはじめ「まえがき」で、
続きを読む 加藤一二三九段に学ぶ、負けても希望を捨てない極意:『負けて強くなる 通算1100敗から学んだ直感精読の心得』読了
高城剛さんが夏(8月)に上梓された『不老長寿』を読了。
” 本書は数百万円をかけて、世界中の最先端医療検査を受けた男の人体実験記録である。それらの中で、日本での検査が可能で、かつ効果的と僕が思うものを書き出した。”(p16)
と、本書の始まり「はじめに」で本が定義されています。さらに読み進めていくと馴染みのない医学的な専門用語が散見され、
読み流すところもありましたが、ショッキングな事実の開示に、認識を改めさせられることが多々あり、例を挙げると・・
” オーストラリアの英語にふれたとき、人間はどこでも同じだと思ったことがあります。
オーストラリア英語は発音が違うでしょう。とても変わった発音です。英語だけれど、「A」を「ア」ではなく、「アイ」と発音する。
またそれを頑なに直さないのです。I come here today が、 アイ・カム・ヒア・トゥダイ に聞こえるので、「今日、ここに来ました」が、I come here to die つまり、「死ぬためにここに来ました」になってしまいます(笑)。
それではラジオはどうかといえば、クイーンズ・イングリッシュ。米語ではなく、きちんとした英語です。
・・中略・・
なぜかと言うと、オーストラリアはもともと流刑地だったところです。刑務所と同じで、先に入っている人が偉い。牢名主っているでしょう?(笑)。
後から来た人を差別するのです。その典型が言葉です。後になるほど言葉は通じなくなってきますから。”(出典『京都の壁』p35-36)
日本ハムファイターズが北海道へフランチャイズ移転後に黄金期を築いた森本稀哲さんの『気にしない。』を読了。
本を読んでまず意外であったのは、ご本人が
” 選手としての成績は、日本プロ野球名球会に入るための条件「2000安打」にほど遠い904安打、「記録よりも記憶に残る選手」と言われれば悪い気はしませんが、今もみなさんから忘れられずにいるのが不思議でありません。”(p3)
と仰られており、自分もしっかり記憶に残されているアスリートですが、
続きを読む 森本稀哲さんが綴った現役選手生活の光と陰、そしてド派手なパフォーマンスで伝えたかったこと:『気にしない。』読了
日本総合研究所会長、多摩大学学長で、報道番組等でコメンテーターとしても活躍されている寺島実郎さんの『ユニオンジャックの矢 大英帝国のネットワーク戦略』を読了。
水曜日に参加した特別講演会が縁で購入した一冊。
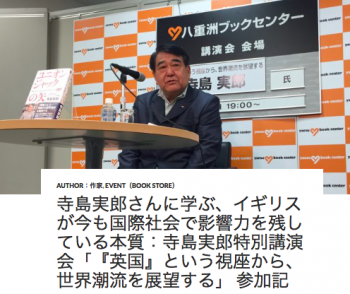
内容も主だったところは講演のおさらいとなりますが、本を開いたところの「はじめに 「全体知」としての英国理解への挑戦」で
” 英国をグレート・ブリテン島に限定した欧州の島国と捉えてはいけないということである。
この国のポテンシャルはネットワーク力にある。”
とくに、五二か国を緩やかに束ねる隠然たる影響力、その中でもロンドンの金融地シティを中核に、
ドバイ(アラブ首長国連邦)、ベンガルール(インド)、シンガポール、シドニー(オーストラリア)を結ぶラインを「ユニオンジャックの矢」とイメージし、その相関をエンジニアリングする力に注目すべきである。”(p3)
という本書の根幹に据えられた見立てに始まり、「ユニオンジャックの矢」とは・・
続きを読む 寺島実郎さんに学ぶ、英国の国際競争力を支えるネットワーク戦略:『ユニオンジャックの矢 大英帝国のネットワーク戦略』読了
養老孟司先生の『京都の壁』を読了。
先日参加したトークイベントに参加する際、
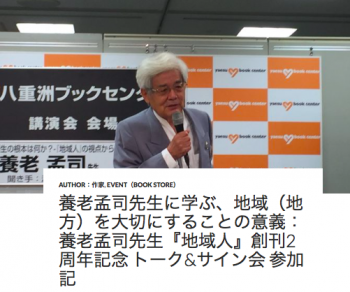
トーク後に開催されるサイン会用に購入した一冊でしたが、
京都から帰ってきて程なくという巡り合わせで、読むにいいタイミングでした。
内容は、鎌倉生まれの鎌倉育ちでいらっしゃる養老孟司先生が、
” 京都以外の出身者から見た京都論というのは、視点が変わっておもしろいかもしれない。そんなわけでこの本の執筆をお引き受けすることにしました。”(p3)
という視点から、
先日、中間記をアップロードした
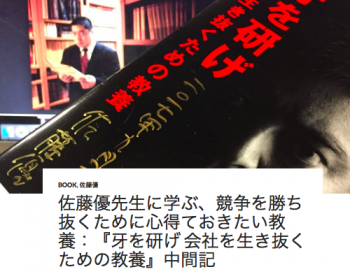
佐藤優先生の「牙を研げ 会社を生き抜くための教養」を読了。
中間記を書いてから後の部分は、
第四章 教養としての地政学
第五章 貧困と資本主義
第六章 ビジネスパーソンのための日本近現代史
第七章 武器としての数学
おわりに 体験的読書術
という構成。
全体的な印象としては、前半(〜第三章)では社会人として「独断専行」の絶対的必要性をはじめとして、
教養というよりは実践的な内容に主軸が置かれているとの感じを持っていましたが、
後半(第四章〜)は、