ひろゆきさんの『これからを生きるための無敵のお金の話』を読了。
週初めに参加したトーク&サイン会👇の対象書籍として入手していた一冊。
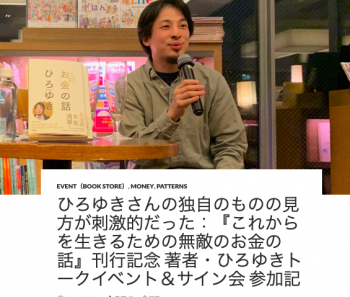
タイトルから「お金」にフォーカスされた一冊と思いきや・・
続きを読む ひろゆきさんが紐解いた、お金持ちになって確信したお金との向き合い方:『これからを生きるための無敵のお金の話』読了
ひろゆきさんの『これからを生きるための無敵のお金の話』を読了。
週初めに参加したトーク&サイン会👇の対象書籍として入手していた一冊。
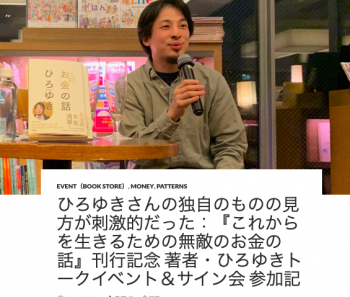
タイトルから「お金」にフォーカスされた一冊と思いきや・・
続きを読む ひろゆきさんが紐解いた、お金持ちになって確信したお金との向き合い方:『これからを生きるための無敵のお金の話』読了
ひろゆきさんの『このままだと、日本に未来はないよね。』を読了。
タイミング良く刊行記念トークイベント👇
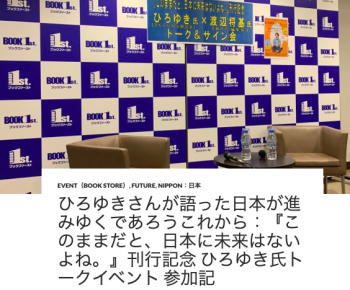
当日に読了していましたが、冒頭「はじめに」で
” 本書では、これから日本がどんなふうにヤバくなるのか、沈みゆく日本で生き抜くためにはどうしたらいいのかを紹介していきます。”(p001)
とあり、前半から中盤にかけて
メディアアーティスト 落合陽一さんの『デジタルネイチャー 生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂』を読了。
本書については書店で発売を知っていたものの、タイトルにパラっと立ち読みした際に
「自分向きではない」と感じていたものの、
先月(2019年2月)開催された個展「質量への憧憬」開催中に行われたトークイベント👇 開演前に

物販ゾーンで本書のサイン本が発売されており、

そのことがトリガーとなって購入に至っていた経緯。
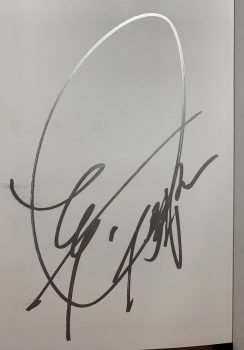
実際に読み始めてみて
” 本書では、<近代>を<イデオロギー>ではなく、<テクノロジー>の側面から乗り越える可能性を考える。
産業革命と資本主義が<近代>の重要な成立要件である以上。その超克も技術的な更新抜きにはありえないはずだ。”(p40)
と本書について説明された一文などからも「難しいなぁー」と、手に取った時の直感は当たっていたものの
続きを読む 落合陽一さんが誘(いざな)う、自然とデジタルが更に融合していく時代の前提と歩み方:『デジタルネイチャー 生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂 』読了
ビートたけしさんの『フランス座』を読了。
昨年(2018年)末、ふら〜っと立ち寄った書店で、本書のサイン本を見つけ
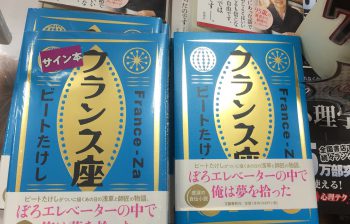
「これは〜!」と反応して、即レジへ向かい購入。
その後、一旦家の中で行方不明となったものの・・ 見つけ出したタイミングで読み始め。
サイン目当てで、内容は二の次というようなところもありましたが、
歴史学者 Yuval Noah Harari:ユヴァル・ノア・ハラリ『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来(下)』を読了.-
下巻を読み始めてから
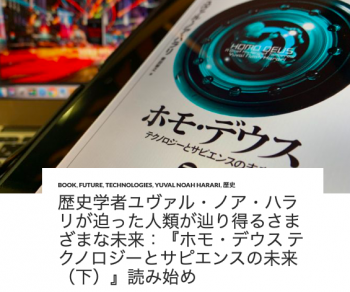
数日前に一旦整理した状況☝️から
読み進めたのは 第3部 ホモ・サピエンスによる制御が不能になる になりますが、
これまでの苦戦が大幅に解消され、
” 二一世紀には、私たちは新しい巨大な非労働者階級の誕生を目の当たりにするかもしれない。
経済的価値や政治的価値、さらには芸術的価値さえ持たない人々、社会の繁栄と力と華々しさに何の貢献もしない人々だ。
この「無用者階級」は失業しているだけではない。雇用不能なのだ。
・・中略・・
人間がアルゴリズムよりもうまくこなせる新しい仕事を生み出すというのが、重大な課題なのだ。”(位置 No.2415/2435)
” 私のことを私以上に知っていて、私よりも犯すミスの数が少ないアルゴリズムがあれば十分だ。
そういうアルゴリズムがあれば、それを信頼して、自分の決定や人生の選択のしだいに多くを委ねるのも理に適っている。”(位置 No.2508)
といった
Yuval Noad Harari:ユヴァル・ノア・ハラリが示す蓋然性の高い近未来に言及した件(くだり)が多く、本書に興味を持った時点で期待していた内容で読み応えありました。
紙の本では567ページに及ぶ分かり良いまとめは、巻末の「訳者あとがき」で柴田裕之さんが端的にまとめておられ、
こちらでは別途、私的に印象的であった部分を抜粋すると・・
続きを読む 歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリが迫った人類が辿り得るさまざまな未来:『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来(下)』読了
(2019年)2月23日時点の積読状況。
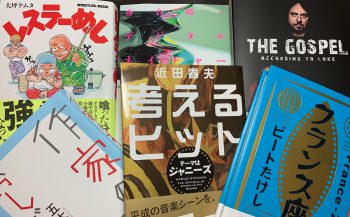
Yuval Noah Hariri:ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福』
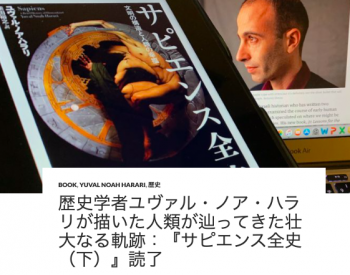
『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来』
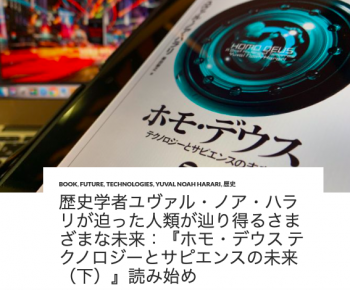
の各上下巻(計 約1,150ページ)読了目処がようやく立ち、「その前後で買っていた本が溜まってきたなぁ(苦笑)」と。
書店に立ち寄って「何か、出ているかな?」と売場を彷徨う必要がないことは有難い状況も、
歴史学者 Yuval Noah Harari:ユヴァル・ノア・ハラリ『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来(下)』を読み始めて
第2部 ホモ・サピエンスが世界に意味を与える
第6章 現代の契約
第7章 人間至上主義革命
第3部 ホモ・サピエンスによる制御が不能になる
第8章 研究室の時限爆弾
第9章 知識と意識の大いなる分離
第10章 意識の大海
第11章 データ教
と収録されているうちの第2部を読み終えたので、そこまでのおさらい。
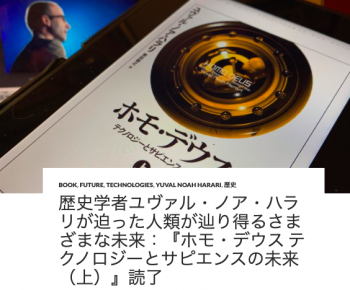
世界史実からの引用が目立ち、相変わらず難しいですが(苦笑)
そんな中で、
続きを読む 歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリが迫った人類が辿り得るさまざまな未来:『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来(下)』読み始め
歴史学者 Yuval Noah Harari:ユヴァル・ノア・ハラリ『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来(上)』を読了。
原書は日本語版と異なり、上下巻となっていないこともあり、上巻最後は
” 本書ではこれからの二章で、科学と人間至上主義との間で交わされた現代の契約の理解にもっぱら努めることにする。
そしてその後、最後の第3部では、この契約が崩れかけている理由と、その後釜に座るかもしれない新しい取り決めを説明する。”(位置 No.3753-3762)
と、展開されている論の中途というところ。そこに至るまでも全般やはり難しめながら、
前回👇から
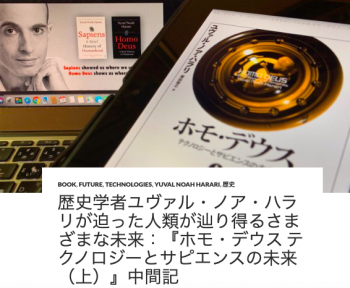
読み進めたところ(第1部 第3章 生命の方程式〜)から、興味深いところを以下に引用してみると・・
続きを読む 歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリが迫った人類が辿り得るさまざまな未来:『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来(上)』読了