門田隆将さんの『裁判官が日本を滅ぼす』の全431ページを読了。
中間記⬇︎後、

読み進めた第八章から第十四章は、個別の事例(ときに類似事例を含む)をもとに主として禁じ得ない違和感、国民感情との乖離について言及され、
終章となる第十五章では、そもそもどういう人たちが裁判官に任官し
” 裁判官は、年齢が若く、成績が抜群で、しかも従順な人間を主にピックアップしていきますね。成績上位者は、裁判官になることが多い。”(p372)
そこから
” 裁判官一人が抱えている訴訟件数は、平均およそ百八十件。しかし、これは家庭裁判所や簡易裁判所など、比較的訴訟数の少ないところも合わせてのことで、各地裁レベルでは、二百件から三百件が普通だという。”(p366)
といった実情に、
” 裁判官は訴訟を手際よくこなし、上の意向に沿って一定の方向に向いた判決を次々と下していく。彼らにとっては、最高裁判所は絶対。これに反する判決を出すことなど、およそ考えられない。”(p368)
或いは
” 長年、裁判官をやっていれば、人の言うことを聞かず、独善的で、しかも他人に対する配慮がなくなります。”(p382)
等々の片膝つかされてしまう(裁判官の)特質に、、
裁判所の本分
既述のとおり400ページ超のボリュームで、事件の詳細について記された箇所など一部では目を背けたくなりますが、
一章あたりコンパクトに論点が整理され、読みやすく、思いのほか早く読了に至りました。
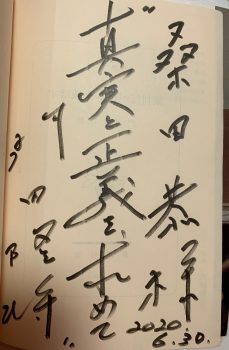
事件が克明に記されている場合、ご遺族に感情移入し、判決で打ちのめされて、、 というパターンを幾度も辿りましたが、
本書に取り上げられていることはどれも他人事ながら、いつ誰しも当事者になり得ること。
栽培員制度で試みられた司法制度改革も当初意図された方向には向かっていない様子から愕然とさせられると一方、
” 日本の裁判を変えていくのは、可能だと思っている。”(p402)
と、門田隆将さんが言及されている根拠となる日本の裁判傍聴制度に違和感を覚えたアメリカ人青年が訴えを起こし、それまで禁止されていた法廷内でのメモ取りを最高裁に認めさせたことを例に、
歩みは遅くとも一人ひとりが当事者意識を持つことで、裁判所が正義の執行される場所として機能することに僅かながら希望を見出すことも出来ました。













