1989年4月出版ながら2021年において再び脚光を浴びているとの


話題のもとは・・
本書冒頭で、主人公の作家のもとへ懇意にしている評論家から
” もしひとつの言語が消滅した時、惜しまれるのは言語かイメージか。つまりは言語そのものがこの世界から少しずつ消えていくというテーマの虚構。
・・中略・・
ひとつのことばが失われた時、そのことばがいかに大切なものだったかが始めてわかる。
そして当然のことだが、ことばが失われた時にはそのことばが示していたものも世界から消える。そこではじめて、それが君にとっていかに大切なものだったかということが」”(p18)
との提案を受け、本書の一章進むごとに五十音が一つずつ消えていくという実験的SF小説。
(次第に文字が失われていくとの)コンセプトは聞いたことあったものの
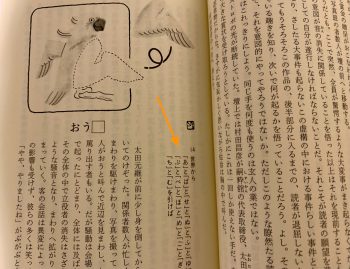
最初はともかく中、後半に至って消えた文字数が多い中でも小説が整理しているのは圧巻。
それを長編で成立させることのハードルの高さは、巻末の「調査報告 筒井康隆『残像に口紅を』の音分布」で、
筒井康隆先生ご自身が執筆に入られる前
” 音はランダムに消えて行きますので、自分の作品にどの音の頻出度が高いかを調べた上で、多少は意図的に消して行かねばなりません。
そこで『虚航船団』の冒頭と、『夢の木坂分岐点』の冒頭の、音の頻度表を作りました。”(p334)
と、ご自身の傾向を自著で把握されたりした準備段階を経て、それでも
” こゝで、ひとたび消した音を後に使うことがなかったかどうかを見るに、第二部までに五件の違反があった。”(p325)
徹底出来ていなかったとの「調査報告」を担当された泉麻子さん、水谷静夫さんの指摘に、改めて創作の難しさを。
長編で堪能した醍醐味
もっとも読書している限り、そうした点まったく気にならず、発想に実践に、筒井康隆先生のチャレンジングな姿勢、真骨頂を感じた次第。
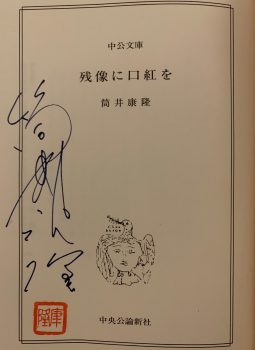
このところ短編やエッセイ中心で、300ページ超に及ぶ長編を読んだのも久方ぶりであったろうと、この点での読み応えも得られた著書でした。













