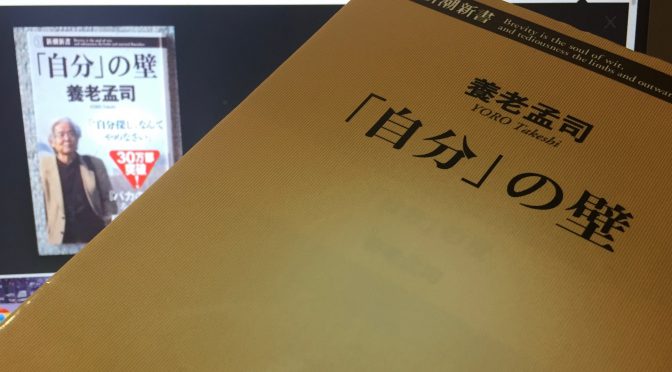養老孟司先生の『「自分」の壁』を読了.-
だいたい1ヶ月で『京都の壁』『バカの壁』『超バカの壁』と、4冊目の養老先生本の読了となりましたが、本書は
” 「自分」という話題は、以前から考えていました。変に聞こえるかもしれませんが、幼稚園のころからです。
自分はなんだとか、自分はどんな個性の人間だとか、そういうことを考えたわけではありません。
自分はなんだか世間と折り合いが悪いけど、いったいなにが問題なんだろう、というようなことです。”(p3)
といった幕開けから
例えば「個性」について言及した
” 世間に押しつぶされそうになってもつぶれないものが「個性」です。
結局、誰しも世間と折り合えない部分は出てきます。それで折り合えないところについては、ケンカすればいいのです。
それで世間が勝つか、自分が勝つかはわかりません。でも、それでも残った自分が「本当」の自分です。
「本当の自分」は、徹底的に争ったあとにも残る。むしろ、そういう過程を経ないと見えてこないという面がある。
最初から発見できるものでも、発揮できるものでもありません。”(p33-34)
例えば「意識」に関して
” 意識というものは、自分の体を把握するためにできたものではありません。もっとも原始的な意識は、外界に対応するため、環境に適応するためです。
本来は遺伝子が環境に適応するわけですが、その適応はとても長い時間、何世代ぶんもの時間がかかりますから、もっと現実の環境に適応するのには脳が必要だったわけです。
そのために進化したのが人間の意識です。
それ以外には、意識は根本的に他人の行動や思考を理解するためにある。自分の体の把握のためではないのです。”(p161)
と、言葉は知っていて、会話でも当然のごとく使っていたことについて「へぇー」となる話に、
さまざま養老孟司先生のアングルを通じての考察が、本書でも興味深かったです。
なお、本の結論的なところでは、
” 他人とかかわり、ときには面倒を背負い込む。そういう状況を客観的に見て、楽しめるような心境になれば相当なものでしょう。
自分がどこまでできるか、できないか。それについて迷いが生じるのは当然です。特に、若い人ならば迷うことばかりでしょう。
しかし、社会で生きるというのは、そのように迷う、ということなのです。
どの程度の負担ならば「胃袋」が無事なのか、飲み込む前に明確にわかるわけではありません。その意味では、運に左右されるところもあるし、賭けになってしまう部分もあるでしょう。
なにかにぶつかり、迷い、挑戦し、失敗し、ということを繰り返すことになります。しかし、そうやって自分で育ててきた感覚のことを、「自信」というのです。”(p220-221)
という具合。
「自分」について考え深める221ページの旅
上梓が、2014年6月と他の著書と比較すると新しめで、用いられている事例が身近に感じられたり、
あとは誰しも考えるであろう「自分について、どのように考えるか?」といったテーマ設定が
読み始めの段階から、本と自分自身の距離を近づけてくれ、読了までの221ページ、思考を旅させられるかの感じが心地良かったです。